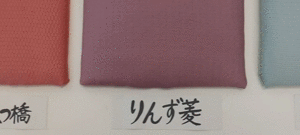手織りによる高度な織技術
通常の平織りは、経糸1本と緯糸1本を交互に交差させて織るため、糸の組織が縦と横で構成されるが、亀綾織は斜めに構成される「斜文織(綾織)」という織り方によるものである。
交差させる経糸と緯糸はそれぞれ3本以上を用い、亀綾の中は数十本の組み合わせになっているものもある。
地紋は足元の踏み木で踏み分けてつくるため、大変高度な織技術を要する。
細い生糸で織り、大変強い力で打ち込むため、20〜30cm織り上げるのに早くても丸一日かかる。着物生地1反ともなると、計画から糸の糊付けなどの作業も経て、完成までは約4カ月ほどかかる。

後練りによる独特の風合い
亀綾織の特性として、無撚り(よりのない糸)の生糸で製織していたことが挙げられる。
これは、後練り織物といわれるもので、絹糸に付着している膠質分(セリシン)をつけたまま製織し、織物になってから精練によりこれを除去すると言う方法をとっている。織上げ後の精練によって、経・緯糸はふっくらとした状態となって、一種独特な風合いと、光沢を持ち、見かけより軽い感じの織物が得られる。
織り上げた後に不純物を洗い落とす「精練」によって生み出される、しっとりとした風合いと気品ある光沢、しなやかな手触りが大きな特色である。

復元した多様な織模様
亀綾織は、最盛時には30数種類の織物が織り出されていたようであるが、現在、それらがどのような織物であったかを推測する手がかりが少なく断定することは出来ない。書物には、さやがた菱・あじろ織・甲亀織・八ツ橋織などの名が残っている。これらは、「織方(タテとヨコの組方、組織)の違いによる名称であったもの」のようである。
江戸文政の頃から新庄藩で特産品として奨励されたが、戊辰戦争による用具の消失により、一時途絶える。授産所を設けて復興されるも、明治末期には生産が途絶え、その後<幻の織物>と呼ばれていた。
1980年代に興った最上モデル定住圏の事業で、地元の特産品として「新庄亀綾織」は織り方の復元が試みられ、残布や織帳の研究から、「紗綾形(さやがた)」等10数種類が復元される。
現在、伝承協会では、大正期頃制作とみられる古文書を手掛かりに、新たな解釈を加えつつ、さらなる織り組織の復元を試みている。
またこれまで、亀綾織の生地を用いた小物を商品化してきたが、伝承協会発足直後から10名前後いた織手も、今現在は2名である。今後、スタッフを充実させ、織手が織りに専念できるようにし、一反ものの着物生地の受注生産を計画しており、予約も受け入れている。